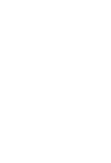備忘
CentOSでRubyをソースコンパイルするときに、いつも事前インストールしているライブラリ群です。個人的にXMLを扱う開発が多いので、XML関連のライブラリも一緒に入れています。
このままコピペして yum install すればまとめて導入できるはず。
openssl openssl-devel readline readline-devel ncurses ncurses-devel gdbm gdbm-devel libffi libffi-devel zlib zlib-devel bison mysql mysql-devel mysql-server sqlite-devel libxml2 libxml2-devel libxslt libxslt-devel libyaml libyaml-devel
[2016.06.04 追記]
Ruby 2.2.1ビルド時にlibffi-develが無くて怒られたので追記しました。
さらにCentOS 7用に mysql を mariadb に変更。
openssl openssl-devel readline readline-devel ncurses ncurses-devel gdbm gdbm-devel libffi libffi-devel zlib zlib-devel bison mariadb mariadb-devel mariadb-server sqlite-devel libxml2 libxml2-devel libxslt libxslt-devel libyaml libyaml-devel
- モジュールのロードに失敗してno screens となるとき
xorg-x11-driversパッケージが入っているか確認する。- インプットメソッドの導入
ibusパッケージをインストール…だが他にも色々必要な感じだったので、とりあえず groupinstall でJapanese supportを入れたほうが早いっぽい。(というか面倒くさくなってこれで済ませた)
あとはお好みのデスクトップを入れればOK。職場の環境はできるだけ軽くしたかったのでXfceを使っています。
VPS試したり再セットアップしたりするときの定番なのでメモる。
セットアップ直後
- sudoでrootになれる権限を持った作業ユーザを作り、作業ユーザでroot作業ができることを確認
- sshdの設定を変更、PermitRootLogin no
- sshdをrestart
- コンソールログインができる場合は、コンソールからrootで入れることを確認して心の平安を得る。
- それはともかくとして作業ユーザでSSHログインできることも確認しておく。
- さらにrootでSSHログインできないことを確認しておく。
確認が終わったら、sshdの設定を再度変更、Port を22以外にしておくとさらに安心。
作業環境を整える
- .bashrcを確認して、いつものaliasをセット。rmとmvは基本的に -i を有効にしておきたい
- ssh-keygen を実行して鍵セットを構築
- ログイン元サーバーの公開鍵を適宜セット
作業ディレクトリ構成は大抵 archives/ (wgetしたものを格納)、 factory/ (wgetで拾ったものを展開、ビルド)、 workspace/ (自作のプログラムとかはここでいじる) の3構成。どーせそのうち tmp/ だとか tmp2/ だとかが増えていくのだけど。
定番アプリの導入 (2014/12/19 追記)
- GNU screen (yum)
- git (yum, 特にcheckinstallなどの導入に必要)
- Subversion (yum, gitで管理するなら不要)
- wget (yum)
- checkinstall (ソースからビルド, http://asic-linux.com.mx/~izto/checkinstall/ )
- gettext (yum)
- rpm-build (yum)
$ sudo yum install screen git subversion wget gettext rpm-build
checkinstallの導入は 64bit 版 CentOS での CheckInstall 導入方法 – akishin999の日記 が適切だと思った。大体いつも手作業で対策して、それゆえ毎回忘れてやり直したりしてたことが綺麗にまとまっている。